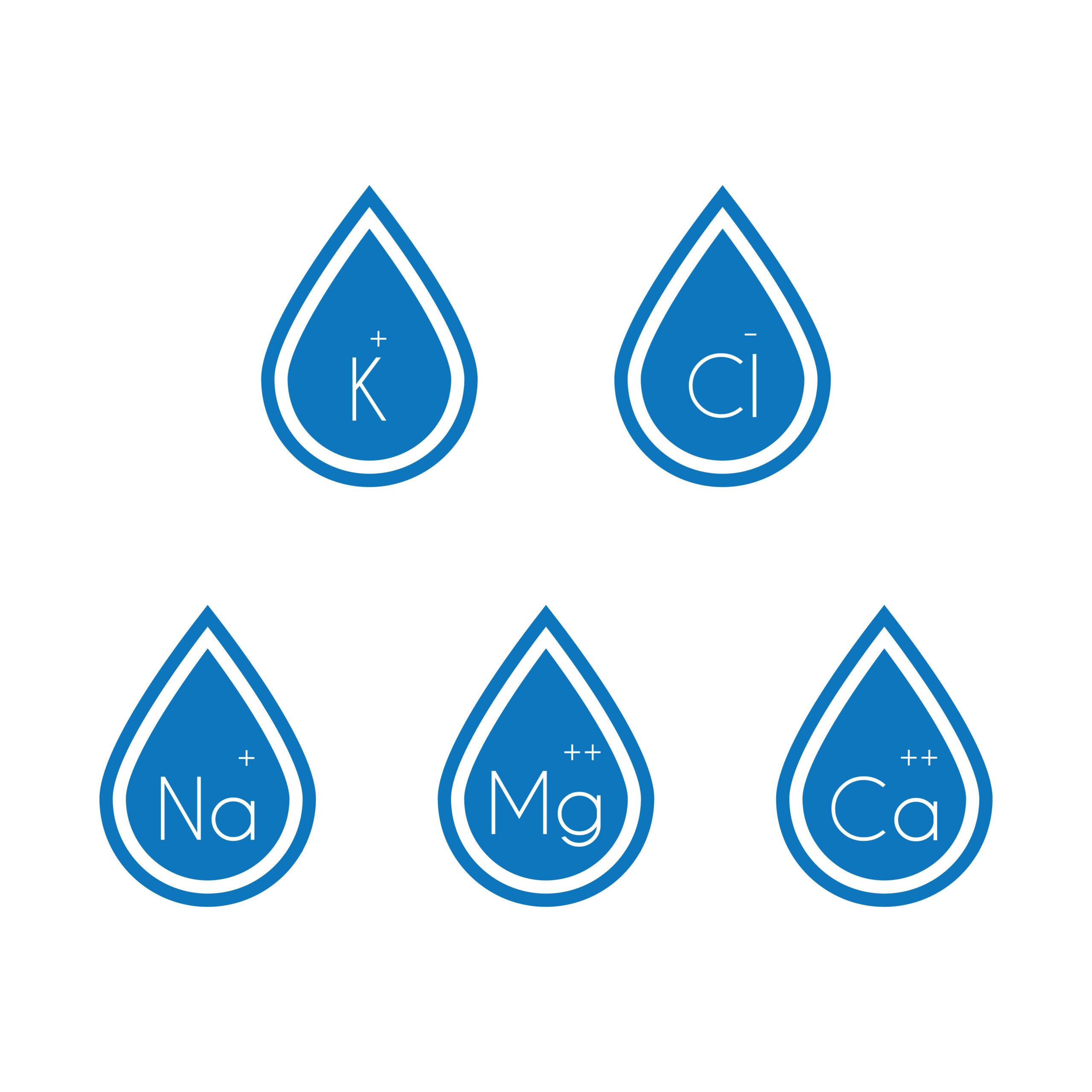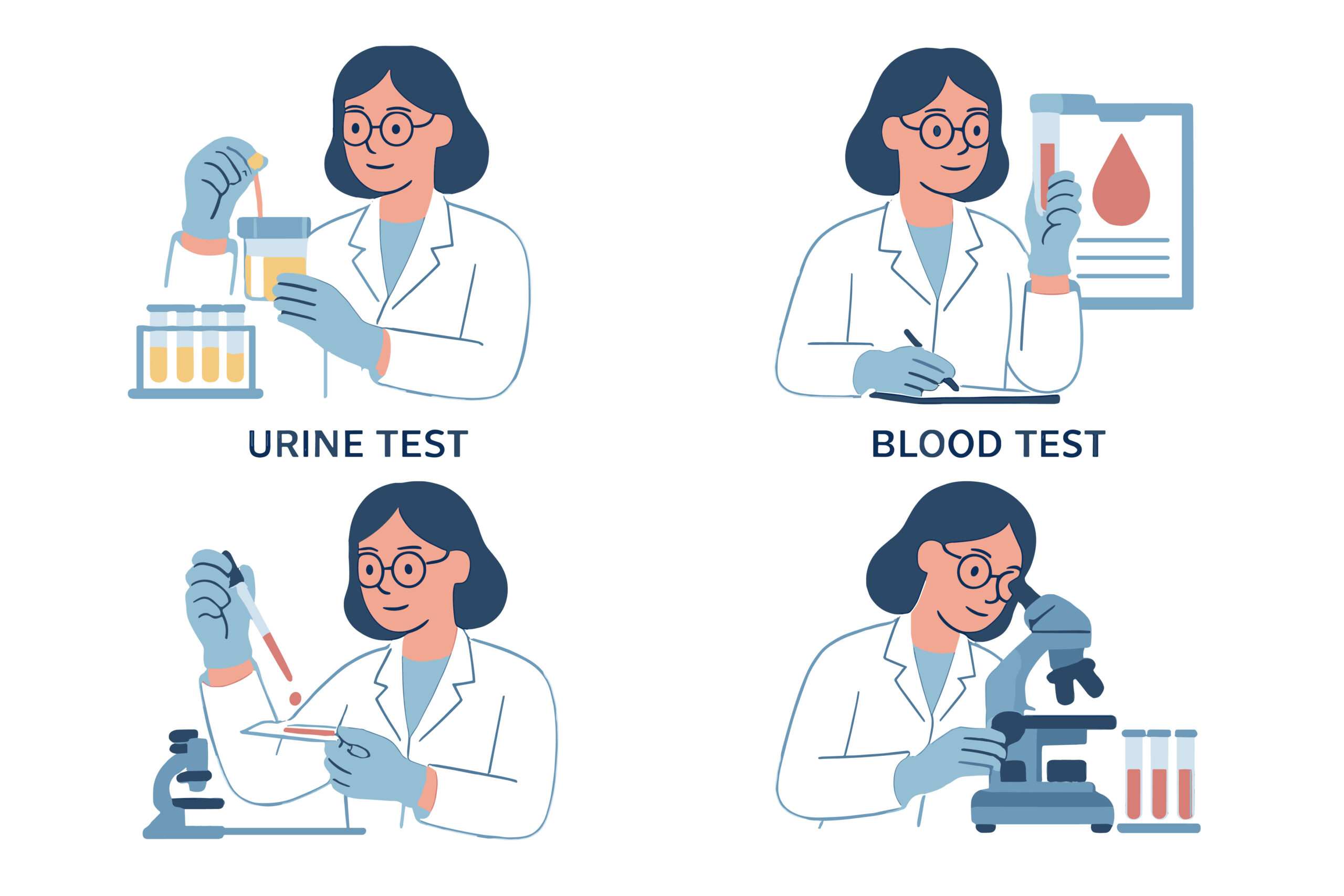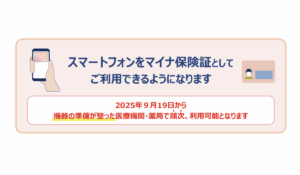「電解質」とは?電解質はとっても大事 ④今日は高Na(ナトリウム)血症 についてお話しましょう。
こんにちは。
医師がもしかしたら病状説明などで自然に言ってしまっている「電解質」・・・
このシリーズでは、そんな「電解質」ついて少しづつお話を進めております。
第4回となる、今回は「ナトリウム」の中でも高Na(ナトリウム)血症です。
高ナトリウム血症は、今までの電解質異常と比べると
比較的シンプルです。
早速見ていきましょう。
もし電解質シリーズ1回目から通して読まれたい方はこちらをご参照ください。
例によってまた復習から参りましょう。
電解質(デンカイシツ)とは?
体液には「電解質(イオン)」が含まれています。
電解質(イオン)とは、水に溶けると電気を通す物質のことです。
主な電解質(イオン)には
・ナトリウム(Na)
・カリウム(K)
・クロール(Cl)
・カルシウム(Ca)
・マグネシウム(Mg)
・リン(P)
・重炭酸(HCO3–) などがあります。
これらは5大栄養素でいうところの「ミネラル」に属します。
ミネラルは水に溶けると陽イオンと陰イオンに分かれます。
例えば、
塩化ナトリウム(NaCl)は
水に溶けると
ナトリウムイオン(陽イオン)と
クロールイオン(陰イオン)になります。
この電解質(イオン)はそれぞれ
・体内のPHの調整
・細胞の浸透圧を調節
・筋肉細胞や神経細胞の働き
など、それぞれとても重要な働きがあります。
それぞれ少なすぎても多すぎてもよくありません。
高ナトリウム血症(高Na血症)とは?
血清ナトリウム(Na)が 145 mEq/L以上になった状態を指します【1】
実は高ナトリウム血症は
ナトリウムそのものが増えているというよりも
水分が足りないことが原因になることが多いのです【1,2】
低Na血症のときにもお話したように
低Na血症でも高Na血症でも
ナトリウムそのものではなく、水分とのバランスが大事ということですね。
水分の不足や喪失が大きな原因で、高齢者や乳幼児では特に注意が必要です。
症状を見てみましょう。
今までのシリーズで
カリウムは、「心臓」と関連が深く
ナトリウムは「脳神経」と関連が深いとお話してきましたように
高ナトリウム血症も、脳神経にまつわる症状が出ます。
水分が足りないことが原因のことが多いので「口渇」が出ることが多いです。
-
軽症:口渇、倦怠感、集中力の低下
-
中等症:筋力低下、意識の混乱、落ち着きがない
-
重症:けいれん、昏睡、呼吸抑制など生命に関わる症状【1,3】
主な原因はなんでしょうか?
高Na(ナトリウム)血症は、病歴から原因の推察は可能なことが多いです。
水分が出ていってしまう、取れないが主で、ナトリウムのとりすぎは少ないです。
1. 水分の喪失
-
下痢、嘔吐、大量発汗
-
利尿薬の使用
-
高血糖など高浸透圧利尿
- 尿崩症(後述します。)→これだけはやや特別扱いです。
2. 水分摂取不足
高齢者は、そもそも口渇を感じづらく、トイレが近いのを嫌い飲みたがらないので
脱水になりやすいので要注意です。
-
水分を摂れていない
3. ナトリウム過剰摂取
-
医原性(点滴補液の影響)
-
サプリメントや薬剤の影響(稀)
- 大量の塩分摂取
尿崩症とは?(簡単にだけ・・・)
さて、先程原因の中に
「尿崩症」という疾患が出てきました。
尿が崩壊する・・・すこしインパクトの強いネーミングですが
簡単に触れておきましょう。
低Na(ナトリウム)血症の際にも重要だった
尿を抑えるホルモン
抗利尿ホルモンADH(Antidiuretic Hormone:バソプレッシン)がここでも重要になってきます。
(低Na血症のブログの中のSIADHの項をご参照ください。→こちら
尿崩症・・・
という名前の通り
尿が崩壊したようにどんどん出てしまうことをイメージしましょう。
体の浸透圧が高いにも関わらず
不適切に薄い尿を、大量に排泄してしまっている状態
を尿崩症といいます。
抗利尿ホルモンは、脳(下垂体後葉)から分泌されますが
脳からの分泌不全(中枢性尿崩症)と
腎臓での感受性低下によるもの(腎性尿崩症)
があります。
このように尿を貯めるホルモン
抗利尿ホルモンADH(Antidiuretic Hormone:バソプレッシン)の不具合により
尿が大量に、不適切に排泄されることで
水分が体内で不足し
体液が濃くなってしまうため
「高Na(ナトリウム)血症」が
ヒントとなって診断がつくことがあります。
尿崩症に関しては
それだけでブログがかけるほどに
疑った場合のマネジメントはお話することが多岐にわたるので
今回は割愛します。
原因だけサラリと触れると
中枢性尿崩症:頭部外傷 脳炎 全身疾患の下垂体病変(アミロイドーシス 血管炎など)
腎性尿崩症:炭酸リチウムの内服
などです。
今日は高Na血症がメインの話題ですので
高Na血症を診た場合
尿がやたら多く、(そのせいで口渇が激しい)という場合は
尿崩症の可能性を考える必要があるということに留めておきますね。
検査はどんなことをするのでしょうか?
高Na血症は、問診である程度どういうことが起こっているのか確認ができるため
問診が大事ですね。
水分が取れていないかどうか、下痢や嘔吐などはなかったか?などの問診と
舌は乾燥していないか?などの身体診察が基本になります。
その他に血液検査や尿検査を行って状況を確認します。
治療はどうすればよいでしょうか?
基本は 「水分の補充」です。
-
軽症:経口での水分補給(経口補水液など)
-
中等症以上:点滴での補正
水分のバランスを見ながら、適宜利尿剤でコントロール
補液の内容は
塩分を含まない点滴がいいのか
はたまた、高Na血症といえど、脱水補正がメインのため、塩分を含んだ生理食塩水の補液がいいのか?
病態に応じて医師が判断して行います。
* 注意*
なんでもそうですが
急激な補正は体に悪いです。
高ナトリウム血症の補正を急ぎすぎると脳浮腫を引き起こし
けいれんや意識障害の危険があります。
そのため補正スピードは1日10 mEql/L以内が推奨されています【1,2,4,5】。
原因が塩分摂取が多いことの場合はもちろん控えます。
また、尿崩症は尿崩症の原因に応じた加療を個別に行います。
おわりに
今日は、高Na(ナトリウム)血症でした。
ナトリウム(塩分)と水分はいつも一緒に考える必要があります。
そして何事においても
ほどほどに
バランスよくというのが大事ですね。
さて
まだまだ暑いものの
すこしづつ秋の気配も感じられる今日このごろです。
秋は何かを始めるにはとてもいい季節と言われます。☆
心身を整えて新しい季節に備えてまいりましょう!
あん奈
参考文献・リンク
-
Sterns RH. Disorders of plasma sodium — causes, consequences, and correction. N Engl J Med. 2015;372:55-65. 👉 PubMed
-
Yun G, et al. Evaluation and management of hypernatremia in adults: clinical perspectives. Korean J Intern Med. 2022. 👉 PDF
-
StatPearls – Hypernatremia (2025 update). 👉 NCBI Bookshelf
-
UpToDate – Treatment of hypernatremia in adults.(要購読) 👉 UpToDate
-
JAMA Netw Open. Rate of Correction and All-Cause Mortality in Patients With Severe Hypernatremia. 2023. 👉 Full text
参考図書
-
國松 淳和 編『國松の内科学』(金原出版株式会社)
-
清田 雅智 監修/上田 剛士 編集/高岸 勝繁 著『ホスピタリストのための内科診療フローチャート 第2版』(有限会社 シーニュ)
- information
- Dr.あん奈のブログ、医学の小話